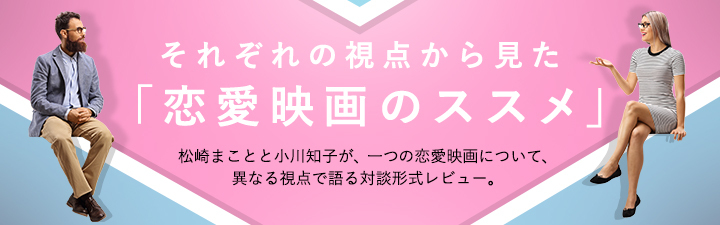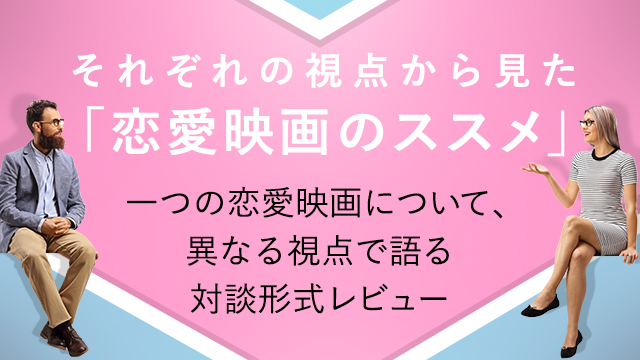それまでのハリウッド映画の常識を覆した記念碑的な名作『卒業』
(C) 1967 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.
ハリウッドを変えた記念碑的な青春ストーリー
『卒業』が映し出す若者たちのリアルに迫る!
2021/12/27 公開
「みんなの恋愛映画100選」などで知られる小川知子と、映画活動家として活躍する松崎まことの2人が、毎回、古今東西の「恋愛映画」から1本をピックアップし、忌憚ない意見を交わし合うこの企画。第10回に登場するのは、ダスティン・ホフマン主演の青春映画『卒業』(1967年)。アメリカン・ニューシネマを代表する本作は、チャールズ・ウェッブの同名小説を基にマイク・ニコルズ監督がメガホンをとり、第40回アカデミー賞では監督賞を受賞している。さらに、ホフマンが主演男優賞、共演のアン・バンクロフトとキャサリン・ロスもそれぞれ主演女優賞と助演女優賞にノミネートされた。
劇中に流れるサイモン&ガーファンクルの楽曲「ミセス・ロビンソン」「サウンド・オブ・サイレンス」は日本でも大ヒット。結婚式場から花嫁を奪い去る場面は、映画史に残る名シーンとしてあまりに有名だ。
大学を優秀な成績で卒業し、将来を嘱望されているエリート青年のベンジャミン(ホフマン)。どこか虚無感を抱え、悶々とした日々を送っていた彼は、父親の共同経営者の妻ロビンソン夫人(バンクロフト)に誘惑され、逢瀬を重ねるように。そんなある日、両親の勧めで仕方なく夫人の娘エレイン(ロス)とデートしたベンジャミンは、純粋な彼女を本気で好きになってしまう。

将来について思い悩むベンジャミンは年上の既婚女性の誘いに乗り、関係を持ってしまう
(C) 1967 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.
モラトリアム期の若者の葛藤や虚無感を映し出し、アメリカン・ニューシネマを代表する作品に
松崎「それまでのハリウッド映画の様式をすべてひっくり返してしまったアメリカン・ニューシネマの代表作ですね。主役が美男美女でないところが、当時のハリウッドでは考えられなかった。アン・バンクロフトはすでにスターでオスカー女優でしたが、ダスティン・ホフマンは本作が初主演で、キャサリン・ロスもほぼ新人女優でした」
小川「ホフマンとロスも十分美男美女ですけれど、それまでのハリウッド映画のいわゆる王道主役という雰囲気ではないですね」
松崎「ホフマンより先に主演を打診されたロバート・レッドフォードが断ったとも言われています」
小川「タイプが全然違いますね」
松崎「『明日に向って撃て!』よりも前だから、レッドフォードもまだスターじゃない頃。マイク・ニコルズ監督がレッドフォードに女の子に振られたことがあるか訊いたら、『そんなことあるわけない』と答えたので、役に選ばれなかったという説もありますね。レッドフォードはどう見ても、年上の女性と相対した時に、オドオドするタイプじゃないですし」
小川「モテる男感しかない。一方のホフマンはベンジャミン役にピッタリでしたね。伝統的なマッチョさではなく、やさしくて、ある種、いい意味で頼りない感じがあって。背もそこまで高くないですし」
松崎「165cmくらいだったかな。アメリカン・ニューシネマの時代が来なければ、スターにならなかったとも言えます」
小川「学生時代に観た時は、自分自身もモラトリアム期間真っ只中ではあったんですけど、正直そんなに衝撃的な映画として残ってはいないんです。でも、アメリカン・ニューシネマが生まれた歴史や文脈を改めて考えると、やっぱりすごいことだよなと」
松崎「そうですよね。ハリウッド初のモラトリアム映画と言ってもいいくらいの作品。この作品の登場人物以降、このような主人公が普通に描かれるようになったわけです」
小川「そういった物語が世の中を動かして選択肢を増やしてくれたから、自分もモラトリアムを当たり前のものとして享受できていたんだなと思いました」
松崎「僕が最初に観たのはテレビ初放送の頃。この映画は1967年にアメリカで公開されて68年に日本で公開。その9年後の77年に吹替えで観たのが初めてでした。かつてはテレビで放送されるまですごく時間がかかったんです。当時中学1年生で、モラトリアムも何もわからないで観ているわけだから、衝撃ではあったけれど、映画史的に外せない映画であることは後で知るという感じでした。それこそ、あの有名なラストシーンがいかに多くの作品でパロディにされてきたかを考えたら、すごいですよね」
小川「ここ2、3年の韓国ドラマでも『卒業』の花嫁連れ去りやバスのシーンが元ネタなんだろうなという作品いくつか観ました」
松崎「そういう使われ方をするのも『卒業』が最初だったくらい、とにかくここから始まったものってめちゃくちゃ映画史的に多いです」

ベンジャミンと関係を持ち、彼の父親の共同経営者の妻でもあるロビンソン夫人
(C) 1967 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.
子ども時代との決別。不安を抱えながら社会への一歩を踏み出すこと
小川「私はこの作品の少し後に生まれていますけど、子ども時代からの卒業という意味では共感するところはあった気がします。学生時代は、わからないことが多いからこそ、いろいろ挑戦して模索していましたし。根拠のない自信しかないから、未来へのものすごい不安も募るシーズンというか」
松崎「自分が何者でもないという悩みですよね。ハリウッドが1950年代から60年代前半までに描いたものっていうのは、要するに、ちゃんと社会に出て真面目に働き、結婚して家庭を築き子どもをもうけ、郊外に一戸建ての家を買って、というのが白人社会の当たり前になっていた。だけど、アメリカン・ニューシネマの文脈ではまずそれを一つ破るわけです。大学は出たけれど、僕は一体何を勉強してきたのだろうってね」
小川「きっと誰もが一度は抱えたことがある悩みかもしれないですね。何者かになりたいけれど何になりたいかはわからないとか、自分だけじゃなく、ひいては自分が生きている場所だったり、国だったりがこれからどこへ向かうのかわからない、みたいな不安はすごくよく描かれていますよね」
松崎「私が大学生だったのは80年代後半だけど、知っている年上の女性に誘惑されてドギマギしちゃう童貞なんていうのは、周りにもいましたね(笑)」
小川「いるでしょうね。しかも彼女も裕福な生活を送ってはいるけれど、不満があるんですよね。かつては自分の夢があったけれどそれを叶えることなく結婚し、子育てに追われるうちに夫とはセックスレスになり、外でその不満を解消するというのは、現代でもまあよく聞く話です」
松崎「ミセス・ロビンソンも学生時代に美術を学んでいたという設定は、要するにベンジャミンと同じような人だったのに、妊娠ですべてを諦め、専業主婦になったのに夫とうまくいかず渇いてしまい、アル中になっちゃう的な。ベンジャミンとは男性、女性の違いはあるけれど、50年代、60年代のアメリカが描いてきたものの裏返しというのかな。表向きは幸せな専業主婦だけど…という」
小川「内情はこうですよってことですよね」
松崎「要するにダメな大人社会がベンジャミンに侵食していく様子を描いている。誘惑してくる女性が童貞のベンジャミンにとって魅力的だったから、それに乗っかっちゃって溺れちゃうという」
小川「溺れてはいるんだけど、不倫の関係であっても何か確かなものを築こうとしているベンジャミンとロビンソン夫人との温度差がコミカルに描かれていて。魅力的な若い身体しか求められていないわけだから、ベンジャミンの虚無感は募るし、本質的なコミュニケーションを求めては肩透かしを食らう。あのシーンはリアリティがありました」
松崎「ギャグ満載でコメディとして成立していますよね。ニコルズ監督のセンスもあるけれど、ホテルのフロント役で出演している脚本のバック・ヘンリーの力も相当影響していると思います」
小川「素敵なフロントマン!」
松崎「物書きとしても役者としても有名な人だけど、のちに『天国から来たチャンピオン』ではウォーレン・ビーティと共同監督も務めているし、1990年代にはニコール・キッドマン主演の『誘う女』の脚本も書いています」
小川「あのホテルも、あそこしか選択肢がないんだろう感ありますよね。後日、エレインを連れてくる時に常連扱いされて逃げ出すところも笑えます」
松崎「田舎のラブホで鉢合わせじゃないけど、そんな気分ですよね。関係性は別にして、年上の人に教わらないとわからないことってあるよな、なんて思いながら観る映画でもあります」
小川「そうそう。愛情のあるなし関係なく、お金を持って使ってみないとわからない、体験しないと知ることができない、人生のお作法みたいなものってありますしね」
松崎「映画に出てくるのは基本、中流の上のほう、もしくは上流の下あたりで、そこそこのお金を持っている人たちだから、違和感はないよね。息子にアルファロメオをあげちゃうくらいだから」
小川「ずっとプールでプカプカ浮いていたい感じのモラトリアム時代、自分にもあったので。すごくよくわかります。このままできる限り地に足をつけたくない…みたいな(笑)」
松崎「社会に出たくない、出なきゃいけないとわかっているけれど、怖くて出られないっていうね」
小川「自分はまだ何もしてないのに、世の中の大人然とした大人が薄っぺらく見えて、そういう人にジャッジされたくないと感じていた気持ちを思い出しました」

ロビンソン夫人の娘、エレインに惹かれるベンジャミン。夫人との関係を彼女に告げるが、拒絶されてしまう
(C) 1967 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.
松崎「水のシーンが多いのもこの映画の特徴で、羊水を表しているらしいです。母親の子宮から出たくない的なことを言っているわけです。初体験後に黒メガネをかけるのも、悪い世界を覗いてしまったことを表現していて。このあたりも後の映画でいっぱい引用されています」
小川「そして、ラストシーンですよ。2人で式場から飛び出したのはいいけれど、最後の微妙な表情はやっぱり忘れられないですね。笑顔で全てうまくいくことがいいエンディングなわけじゃない作品の代表というか」
松崎「あの2人はきっとうまくいかないだろうと言われ続けていましたから。いい大学に入れてもらって、お金も潤沢に注いでもらっていた場所から2人で抜け出しちゃおうというのがまさに60年代の終わり、70年代に向かっていく話です」
小川「親へ反抗し、親離れした若者たちの拠り所として、ヒッピーカルチャーがあったんでしょうね」
松崎「核家族になっていく感じも出ていますよね。晴々とした笑顔から急に真面目な顔になる。世の中に立ち向かっていかなくちゃいけないという決意表明でもあると言われています」
小川「決意表明ほどはっきりしたものかはわからないけれど、半歩先の現実が見えてきたんだなぁと思いました」
松崎「ガス欠して車を乗り捨てるところも、親がくれたものを捨てることを意味しているし」
小川「ラストシーン同様、楽曲もすばらしくて。『さよなら、僕のマンハッタン』でもサイモン&ガーファンクルの曲が流れていて、あれも『卒業』のオマージュ作品でしたね」
松崎「50年経ってもいまだに影響を及ぼしているすごさを感じますね」
小川「もはや元ネタを知らずに観ている人もいるかもしれないくらい、語り継がれている。まさにレジェンドですね」
取材・文=タナカシノブ
松崎まこと●1964年生まれ。映画活動家/放送作家。オンラインマガジン「水道橋博士のメルマ旬報」に「映画活動家日誌」、洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」HP にて映画コラムを連載。「田辺・弁慶映画祭」でMC&コーディネーターを務めるほか、各地の映画祭に審査員などで参加する。人生で初めてうっとりとした恋愛映画は『ある日どこかで』。
小川知子●1982年生まれ。ライター。映画会社、出版社勤務を経て、2011年に独立。雑誌を中心に、インタビュー、コラムの寄稿、翻訳を行う。「GINZA」「花椿」「TRANSIT」「Numero TOKYO」「VOGUE JAPAN」などで執筆。共著に「みんなの恋愛映画100選」(オークラ出版)がある。
<放送情報>
卒業
放送日時:2022年1月11日(火)21:00~、24日(月)21:00~
チャンネル:ザ・シネマ
※放送スケジュールは変更になる場合があります
あなたにおすすめのコラム
-

宇垣美里のときめくシネマ
SF 映画の金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に 「白紙の未来」は自分次第なのだと力強く背中を押される
2024/04/01
-

ジャッキー・チェン生誕祭
アジアの枠を超え、世界的な大スターに! 70 歳、ジャッキー・チェンの波乱万丈な映画人生をたどる
2024/04/01
-

この俳優から目が離せない
40 歳の若さで逝った伝説… 映画スター、松田優作の俳優としての生き様
2024/03/25
-

今月の韓国映画
「イカゲーム」のファン・ドンヒョク監督作 国の存亡を懸けた真実の物語を描く『天命の城』
2024/03/25
-

事件捜査ファイル
殺人事件に巻き込まれた私立探偵の運命は…? 実際の水利権を題材にしたネオノワールな探偵映画『チャイナタウン』
2024/03/25
-

コミックが生み出すヒット...
超人気ドラマの劇場版『ごくせん THE MOVIE』 失敗を認めチャンスをくれる主人公に背中を押される
2024/03/25
##ERROR_MSG##
##ERROR_MSG##
##ERROR_MSG##
マイリストから削除してもよいですか?
- ログインをしてお気に入り番組を登録しよう!
- Myスカパー!にログインをすると、マイリストにお気に入り番組リストを作成することができます!
- マイリストに番組を登録できません
- ##ERROR_MSG##
現在マイリストに登録中です。
現在マイリストから削除中です。